
[スタジオ術 Ⅱ ] 演劇とシンセサイザー

英国製シンセサイザーのEMS Synthi AKS
.Kimi95 at it.wikipedia, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
[スタジオ術 Ⅱ ] 演劇とシンセサイザー
“#演劇“と”#シンセサイザー“ この突拍子もないキーワードからまず最初に思い出すのは、日本で一番ノーベル文学賞に近かった男、純文学作家にして劇作・演出家の安部公房。私が敬愛する唯一無二の劇作家だ。
さて、それでは何故、安部公房なのか?なのだが、ある時期から安倍氏は自身の演劇作品の音楽を自ら作曲?した。その大きな要因はシンセサイザーの出現だろう。
そういえば、シンセサイザーという言葉に対する概念、ないしはイメージも年代によって随分と異なるものとなっている様だ。
打ち込みとは?
最近の人は「打ち込み系」などと普通に使う。それも特に音楽をやっていない人たちの話。これをお読みの皆さんの中でもいわゆる“若者”に属する諸君は「なんでわざわざこんなことを書くのだろう?」と不思議にすら思われる向きも多いとは思うが、「打ち込み」などという言葉が市民権を得たのは実はごく最近のお話。
業界的には古く(多分、80年代前後)から「打ち込み」という言葉は使われてきたが、音楽に興味のない一般人にそうした言葉が通じる様になったのは90年代、いや、下手をすると2000年代に入ってからではないだろうか?
市場にパソコン(当初はマイコンなどとも呼ばれた)が出回る前、70年代後半〜80年代初頭の話だが、シンセサイザーを自動演奏させる為の機械(シーケンサー)は数限られており、その中でも数台のシンセサイザーを同時にコントロールできる機種はローランド社のデジタルコンポーザーMC-8(当時の定価、なんと120万円!)一択と言っても過言ではなかった。

Roland MC-8
Strettamgd (talk · contribs · uploads), CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons
MC-8は電子計算機の様なテンキーで、譜面の情報(音符の高低や長さ)を数字に変換してデータ入力していくのだが、その様子を「打ち込み」と称したらしい。実際のところ、私自身もまだ子供の頃の話なので“こうした説”を何処かで読んだことがあるというのが正しい。真偽はさておき、納得させるに充分な説であるのは確かだ。
シンセサイザーは万能か?
まあ、それはともかく、ちょっと昔に遡ると「シンセサイザーはどんな音でも作れる」という神話がまことしやかにアチラコチラのTVや雑誌で語られたものだ。ちなみにサンプラーすらまだない時代の話。
まあ、広告宣伝媒体としてのメディア的には“有り”なのだろうが、こうした「どんな音でも作れる」という誤解は些か困った事態を招く要因にもなりかねない。
99年に前進座さんの三好十郎作「噛みついた娘」の音楽を担当した際、演出の津上忠先生から「太鼓(和太鼓)の音を入れたい。シンセサイザーかなんかで作れるんでしょ?」とのご要望があった。こめかみ辺りに些か不安が過ぎったものの、とりあえず言われた通りにやってみた。ところが案の定、「これ、太鼓の音じゃないでしょう?」 そう、不安は的中した。
その頃、すでにサンプラーは存在したし、それなりのものを使用してもいたのだが、和太鼓の音の良いサンプル(フロッピーディスクで販売されていた)が見つからず、当時リアルとされていたシンセサイザーの和太鼓の音を使ったのだ。実際、単体で聴くとなかなかリアルな音だったと思う。
だが、前進座はもともと歌舞伎から派生した劇団、そうした劇団の演出を長年手がけてきた津上先生にしてみれば、シンセサイザーによるリアルな?和太鼓の音は偽物以外の何物でもなかったという訳である。
もちろん、現在のサンプリング素材は当時のそれとは比べ物にならないレベルであり、演劇公演の音楽・効果に録音物を使用するという前提であれば、充分に本物の太鼓の音に匹敵する効果が得られるのは言うまでもない。
シンセサイザーの可能性について
だが、よく考えてみれば、実際の楽器では得られない様な音が出せるのにも関わらず、わざわざ既製の楽器音をシミュレートする為にシンセサイザーの可能性に制限を設ける大義は何処にあるのだろう?
そもそも音楽は、抽象的なイメージを音という具体的な形で表現する芸術ではなかったのか? 音楽史的視点で言えば、その時代ごとに可能な技術的可能性を追求してきたのが作曲家でなかったのか?
シンセサイザー誕生の経緯と関連付けて、“音色”を中心に分かり易い例を出すならば、古典作品(ハイドン、モーツアルト等)との比較で、19世紀後半〜20世紀のワーグナー、R・シュトラウスといった後期ロマン派を経由して、印象派のドビュッシー、ラヴェル、更にはストラヴィンスキー等を是非、お聴きいただきたい。その“音色”という1点だけを取り出しても、その可能性の探究が如何に行われて来たのかがお分かりいただけると思う。
その後、20世紀の現代音楽(※現代の音楽ではなく、クラシック分野の前衛音楽の意。ロマン派、フランス印象派、現代音楽といった様に使われる)の一つの流れとして、電子音楽等も生まれてくる。こうなると、もはやシンセサイザーの世界のお話ではあるのだが、それはまた別の機会に。
ここで言わんとしているのは、目的と結果が逆になってどうする?ということであって、シンセサイザーの活用によって、ピアノやバイオリン等の仕組み、もっと言ってしまえばドレミファソラシドすら不要となるという点である。
ドレミファソラシドよりも遥かに無限の響きが、ダイヤルを回すだけで得られるのだからそれを利用しない手は無いというお話。そもそも無限に存在する響きの中から一部を切り取って、コントロール可能なところに落とし込んだのがドレミファソラシドとも言えるわけで、必ずしも音楽=ドレミファソラシドとは限らないのだ。これは西洋近代に俗されているある種のコンプレックスと言えなくもない。
無限の響きの中から自分の耳で選んだ音をテープに記録することが出来るのだ。これが、私の言うところのスタジオの仕事。まあ、現代は記録装置にテープすら使わなくなったが。
演劇人でも大丈夫! 安部公房の“音素材の調理法”?!
そこでシンセサイザー活用による安部公房の本質的かつ先見の明が、演劇人[1]にとっての音楽における一つの雛形となりうるのではないかと考える次第である。
どうやら、安倍氏はシンセサイザー[2]をいじって偶発的に生じた音を素材として録音しておき、それらを後に構成していくことで“一定のまとまりのある音=音楽作品[3]”を構築=作曲?していた様である。
今ならコンピューター一つで簡単に出来る手法[4]である。しかも、いわゆる音楽的知識(譜面の読み書き、各種楽理等)が無くても、耳が聴こえさえすれば感性だけで“それらしいもの”を作ることも容易い。
だが、“作る”のは容易くとも“創る”のが簡単かどうかはまた別の話。
こうした文脈を踏まえ、音楽制作における“非効率のススメ”を書いていこうというのが、本連載“スタジオ術”だったりするのだが、この“非効率”というのが“自分と向かい合う時間”を生み出したりするもんだから、そう馬鹿にしたものでもありません。
もちろん、ここで言う“非効率“はあえて戦略的な意図を持つ訳であるからして、単に不便に終始してしまっては元も子もない。
モノ作り(=創り)には、常に情熱と冷静さが求められます。
そこで、こう考えて頂ければよろしいかと思います。
“実践面=情熱”、そして“理論面=冷静”と。
という訳で、そうした意図を実際の創作現場に上手いこと反映させる為にも、次回以降、実践面を視野に入れつつ、あえて理論的な面もご紹介していければなあと考えている次第であります。
(文: 関口純 ※文章・写真の無断転載を禁じます)
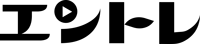
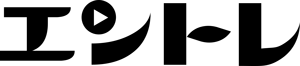



![[スタジオ術 Ⅰ ] 劇場を捨て、スタジオに籠ろう!? 〜日常と世界が交差する場所〜](https://demo013.meteodesign.co.jp/wp-content/uploads/2022/02/image0-300x300.jpeg)

